2016/06/08
C+Bousai vol1
「対策」ではなく「思想」を創る
戸別津波避難カルテづくりでは、地区の細分化によるさまざまな利点が見えてきたという。例えば近所の出席状況が明確なため、欠席がしづらいこと。大人数でないため、1部の住民が活動を怠るといった「社会的手抜き」が排除できること。班単位のワークショップによるコミュニティの活性化や、カルテに記入することによって、記憶に定着化することなどだ。
「取り組みを開始した当初は、お年寄りは津波が来ても“逃げない”ことを自慢するような町だった。少なくとも今は逃げないことがどれだけ家族に迷惑がかかるか、恥ずかしいことかが分かり、みんなが前を向いて防災に取り組んでくれるようになったと思う」(情報防災課長の松本氏)。

地区防災計画策定に向け、説明会を開始
「カルテ」を作成した黒潮町が、次に取り組むのが地区防災計画策定だ。2014年7月22日時点では5カ所に説明会を行い、4カ所から作成するという返事をもらっているという。
「住民も、やることをやらないと行政に期待することはできない。地区防災計画は、私たちの手でしっかり作っていきたい」。海沿いに面する田ノ浦地区での「第2回地区防災計画説明会」で、区長の濱口正海氏は地区防災計画策定に対する意気込みをそう語ってくれた。
黒潮町はこれまで、津波浸水危険区域を中心に津波避難計画を作ってきたが、この地区防災計画制度を期に山間部の土砂災害や河川の氾濫など、町内の全ての災害に対応できるような地域防災計画をまとめあげたいと考えている。
「61カ所すべての地区で地区防災計画を策定するには、おそらく最低でも2年くらいかかるでしょう。ワークショップも、少なくとも900回は実施されると予想している。専門のコンサルタントが入ればもしかすると10回くらいで終わるのかもしれないが、住民が自らの手で作ったというプロセスが大事だと思っている」(松本氏)。

最終的に黒潮町が目指すのは、地域コミュニティの活性化だ。昨年は町ではなく消防団が防災シンポジウムを主催し、国土強靭化担当大臣の古屋圭司氏や内閣官房参与で京都大学大学院教授の藤井聡氏が駆けつけたほか、安倍晋三総理からも激励のメッセージが届いたという。防災を24時間356日考え続けると住民も疲れてしまう。コミュニティを活性化させるためのイベントをこれからも企画していきたいとする。
「本当は防災のためには防波堤も欲しい。ただ、あの美しい長さ4kmの入野の砂浜の沖合一帯に高さ34mの防波堤を造ろうと考えたことはないし、住民からもそのような声は上がってこなかった。河川堤防をレベル1※の津波にしっかりと機能する堤防として補強するだけでも、避難時間を5分から10分稼ぐことができる。私たちは海とともに生きてきた。これからもこの海を自慢しながら生きていきたい」(大西町長)。
※レベル1…概ね数十年から百数十年に1回程度の頻度で発生する津波
(了)
C+Bousai vol1の他の記事
- 「対策」ではなく「思想」を創る 住民と900回のコミュニケーション (高知県黒潮町)
- C+Bousai 創刊挨拶、地区防災計画学会 案内
- 特別対談|住民の権利と責任を制度化 自ら考え行動する地産地消の防災
- 市内全域8地区で防災計画 住民主体でガイドブックも作成 (北海道石狩市)
- 地域コミュニティごと防災計画策定 避難所運営計画、防災マップ作成も呼びかけ (香川県高松市)
おすすめ記事
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/07/08
-

-
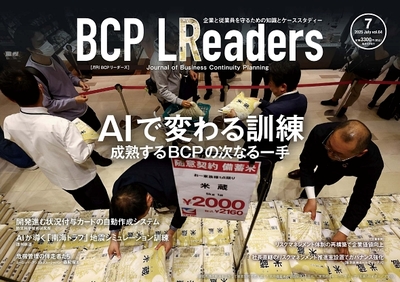
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/07/05
-

-

-

-

-

-

「ビジネスイネーブラー」へ進化するセキュリティ組織
昨年、累計出品数が40億を突破し、流通取引総額が1兆円を超えたフリマアプリ「メルカリ」。オンラインサービス上では日々膨大な数の取引が行われています。顧客の利便性や従業員の生産性を落とさず、安全と信頼を高めるセキュリティ戦略について、執行役員CISOの市原尚久氏に聞きました。
2025/06/29
-



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方