会社のベテラン経理マンの不正を防止するには?
第1回 横領事件の背景と対策

鈴木 英夫
慶應義塾大学経済学部卒業。民族系石油会社で、法務部門・ロンドン支店長代行・本社財務課長など(東京・ロンドン)。外資系製薬会社で広報室長・内部監査室長などを務め、危機管理広報・リスクマネジメントを担当(大阪)。現在は、GRC研究所代表・研究主幹、リスクマネジメント&コンプライアンス・コンサルタント(兵庫)。日本経営管理学会会員、危機管理システム研究学会会員。
2022/08/15
ニュースから探るリスクマネジメントのABC

鈴木 英夫
慶應義塾大学経済学部卒業。民族系石油会社で、法務部門・ロンドン支店長代行・本社財務課長など(東京・ロンドン)。外資系製薬会社で広報室長・内部監査室長などを務め、危機管理広報・リスクマネジメントを担当(大阪)。現在は、GRC研究所代表・研究主幹、リスクマネジメント&コンプライアンス・コンサルタント(兵庫)。日本経営管理学会会員、危機管理システム研究学会会員。

そもそも会社の経理で不正が起きるのは、ベテラン経理マンである。新人は、そんな方法を気づきもしないし、実行するだけの知識もない。ベテランでなければそんな機会も得られないし、やり方もわからず、そもそも不正どころか正確な経理処理さえもおぼつかないかもしれないのである。
同様の事件でしばしば耳にするのが、周りの人たちのコメントで「普段はまじめに仕事していました」とか「上司からも信頼されていました」といった評価である。従って、このような経理不正が起きるにはいくつかの条件がある。
1) 当該業務に精通している
2) 上司からも信頼されている
3) 全てのことが任されて、チェックがなされていない
以上の3要素である。
どんな仕事でもそれを遂行する上で、1)は必要であり、業務に精通していなければ仕事にならない。精通しているからこそ2)上司からも信頼されるのである。であるからして、ここまでは望ましいことであれ、何らの不都合はない。
問題は3)である。全てが任されているのが有効なのは、交渉相手との「瞬時の決断で契約の成否が決まる」といった、営業その他の交渉などの場面である。権限のない担当者との交渉は退屈を超えて、無駄と思われても仕方がない。ところが…である。経理、あるいはさらに職務が分担している会社の場合には「財務」担当の組織においては「全てが任されている」のは仕組みとして既に背任的であろう。
では、経理・財務部門でのリスクマネジメントにはどんな「仕組み」や「心がけ」が必要なのであろうか?
一般に会社であれ自治体であれ、組織がその現預金などの財産について行うことは、二重チェック・承認・複数部署の関与・監査などのモニタリングなど複層的なリスクマネジメントである。例えば、窓口で現金を受け取ったら、必ずその現金と入金伝票を併せて「上席職員のチェック」を受ける。これが二重チェックである。そして、当該取引を終えた時に「上司の承認」を受ける。さらに毎日、終業時に現金を数えて帳簿の残高と一致しているかを確認する。
取引先への支払いについては、通常「担当部門が請求書などの証票を付けて経理部門に伝票を回す」など「複数部門で分担」して業務を行う相互牽制が行われている。さらにITシステムでは、取引先の銀行預金口座は、「取引先マスター」といって別の決済経路でしか変更が出来ないように設計されている。
監査などの「事後のモニタリング」では、資産の記帳や棚卸では、費目により、実在性・網羅性・権利と義務の帰属・評価の妥当性・期間配分の適正性・表示の妥当性などがチェックされる。現金や預金であれば「実在性」が特にチェックされるのである。
ニュースから探るリスクマネジメントのABCの他の記事
おすすめ記事




中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/09



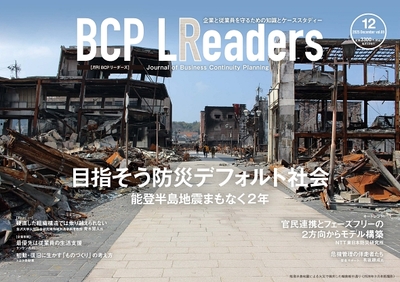
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/12/05

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる
予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。
2025/12/04

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方