2019/04/03
講演録

リーダーシップ
■チームワーク
リーダーシップについて私なりのまとめをします。まず重要だと思うのがチームワークです。全員に役割を与えるべきです。ですが、私が各班のリーダーと話をして、「さっき言っただろう?」と聞くと、同じように伝えていても、隣の班は聞いていても、その班には声が届いていない、あるいは聞いていなかったということもありました。当然皆、自分の班のことで頭がいっぱいなので、いくら大きい声で言っても聞こえていないのです。
■確認と連絡
確認と連絡も大切です。役場の駐車場で待ち合わせというふうに決めておいたのが、役場には表と裏に2つの駐車場があって、それを間違えて夜中4時間会えなかったという情けないことも起こりました。伝える前に現場を確認するなど、日頃から伝え方などを考えておく必要があると思います
■リーダーが責任を取り、情報はリーダーに一元化する
そして、最終的にはリーダーが全て責任を取ってやっていかないといけないと思います。その代わり、情報はリーダーに一元化すべきです。福島第一のテレビ会議の様子を見ていただいた人はお気付きになると思いますが、いろんな人が発言している。やはりあれは吉田(当時、福島第一原子力所長)にとっては非常に辛かったと思いますね。吉田の知らないこともやりとりされているし、吉田の知らないところでいろいろなものが決まっていったりしています。福島第二の様子は公開されたテレビ会議でほとんど出てきていませんが、私しかしゃべっていません。だから私がトイレに行っていたりすると、テレビ会議で呼ばれたときにも、皆が「ちょっと待っていてください」と言って止めて、必ず私を通さないとイエスもノーも言わない。あるいは向こうからの意見も聞かないというような仕組みにしてくれていました。これは後々考えると、とても重要だと思います。だからリーダーが全部理解しているというのは、とても大事だと思います。全ては目的達成のためです。
■覚悟、そして信頼関係
それから、繰り返しになりますが「皆の安全を守る」と言いながらも、最後は危険なところに行ってもらう必要があるんですね。これはやっぱり覚悟を決めなくちゃいけないと思います。
私は30年前にこの発電所に新入社員で入って、ちょっと言葉は悪いですけど、高校卒業の人たちが先輩社員でいて、出来の悪さも性格も、私自身のことも含め、皆が知っているわけですね。私も皆のことを覚えていたんです。現場もその時に駆けずり回って知っていた。それがメリットだったと思います。その30年後に現場に来て、今度は私の部下として、その人たちが所員として残っていてくれた。目を見れば大体通じ合えたというのもありますし、この人が言っている「危ない」という程度が、そういう人に活躍してもらえるということが、非常に大きかったと思います。こうした信頼関係をどう平時から築いていくかが危機対応時には問われるのだと思います。
(2018年11月8日に行われた一般社団法人レジリエンス協会の定例会より)
(了)
第1回 ハーバードで取り上げられたリーダーシップ
第2回 現場の安全を守る
第3回 土地を知っていたことが奏功
第4回 「皆、帰らないでくれ」
講演録の他の記事
おすすめ記事





















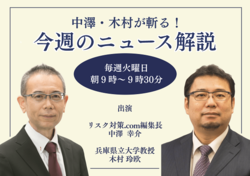














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方