2024/11/18
危機管理ポッドキャスト「日本における人道支援のリスク」
評価チームの派遣
ジョエル:東北での経験を振り返って、もし今の知識があれば、より効果的に交渉し、協力を得られたと思いますか?
チャールズ:今の私なら、最初に行うべきことは「評価チームの派遣」です。そして、支援する地域を決めます。たとえば、400キロにわたる海岸線が被害を受けた場合、どこか一つの地域を選びます。そして、48時間以内に5人のチームを派遣し、5×5キロのエリアをカバーします。つまり、25平方キロのエリアを1時間歩くことでカバーするわけです。最初の48時間で得た情報を基に、「この地域は支援の必要がない」と判断できれば、次の地域に移動します。こうして3つの地域を調査すれば、1週間以内に2つの地域でニーズが満たされていることが分かり、3つ目の地域に対して具体的な支援計画を立てることができます。
ジョエル:なるほど、そのように24時間、48時間、72時間のタイムラインで行動しながら、計画を随時見直し、適応させていくわけですね。でも、最近ではすべてのプロセスがデジタル化され、タブレットやスマホで操作できるようになっています。そうした状況で、戦略的な計画を立てる際のデータの収集や可視化について、具体的なツールや手法はどう考えていますか?
チャールズ:考え方としては3つあります。まず、インターネットが使えない状況を想定した場合、全チームにA4サイズの紙を1枚渡し、確認すべき項目を統一します。たとえば、道路は開通しているか、何パーセントの住民が支援を必要としているか、コンビニは営業しているか、といった具合です。そして、それらの情報を持ち帰り、指令本部に報告します。次に、インターネットが使える場合は、オンラインツールを使って情報を更新できます。最後に、インターネットが使えなくても通信手段があれば、データを本部に連絡し、テキストとして記録します。このデータはAIにアップロードされますが、個人情報は含まれませんので、その点は非常に重要です。AIが素早く情報をまとめ、レポートを作成できます。
ジョエル:それは非常に興味深いですね。たとえば、東京の小規模なNGOやフードバンク、慈善団体が、大きな災害が発生した場合、どのようにしてデータシステムを構築し、可視化するのでしょうか? 手書きのメモだけではなく、より効果的な意思決定や交渉、評価が重要になってくるのでしょうか?
チャールズ:そうですね。たとえ小さなフードバンクや教会でも、10人を2人ずつのチームに分けて派遣し、5×5キロのエリアをカバーできます。25平方キロメートルをカバーすることは、48時間以内にA4サイズの紙1枚で行うことが可能です。そして、その情報をAIに入力し、自組織の能力や目標に基づいて最適な対応策を提案させることができます。また、プリペイドカードを配るなどの限定的な支援を行うこともできますが、最も重要なのは正確な評価を行うことであり、それによって支援の信頼性が向上し、他の利害関係者も効果的な判断ができるようになります。ただし、最初の48時間で人が飢えることはありません。彼らが直面するのは不便さであり、不快な状況であっても、飢えることはないという点を忘れてはいけません。
ジョエル:その点は非常に重要ですね。2013年のセブ島台風での経験もありますが、日本での対応とはどのような違いがありましたか?フィリピンでの対応は、物流や他の条件に起因するミスがあったのでしょうか?
チャールズ:2013年の大型台風ハイヤンでは、世界中から支援が集まり、各国の軍隊も参加しました。私は地元の団体と一緒にセブ島の軍用空港に行きましたが、支援物資が飛行場に山積みになっているのを目の当たりにしました。2011年の東北での経験から、「適切なタイミングでない支援物資が供給チェーンを詰まらせるだけで、誰の役にも立たない」という教訓を学びました。そのため、私たちは日本からの支援を、受け入れ態勢が整った地域に届けることを重視しました。その結果、支援の到着が遅れることもありましたが、むやみに急いで送るよりも効果的でした。
ジョエル:それは、いわゆるサプライチェーン管理の一環ですね。物流会社や民間企業は日常的にそういった管理を行っていますが、小さなNGOやフードバンクでは、そのような知識を持つのが難しいかもしれません。
プッシュ型とプル型
チャールズ:そうでもありません。実際に自分たちでフードバンクやパントリーを運営し、物流管理システムを持っていれば、災害対応の場面でもそのスキルを活用できます。ここで大切なのは、「プッシュ型」と「プル型」の2つの概念です。通常のフードバンクでは、サプライヤーから余剰食品を受け取り、それを下流にプッシュしていきます。災害時には、このプッシュ型から、被災者のニーズに基づくプル型に切り替える必要があります。つまり、支援が必要な人々の要望やニーズに基づいて供給を行うということです。2011年当時は、こうした考え方が不足していましたが、その後の経験を通じて、供給管理の考え方を取り入れるようになりました。
ジョエル:災害の種類やその国のインフラによって、資源管理の難しさは変わってくるのでしょうか?日本において、他の地域とは異なる固有の物流課題があるのでしょうか?
チャールズ:はい、といいえ、両方あります。まず、日本には非常に洗練された物流システムが存在しますので、物資が被災地に届くまでの流れ自体は問題ありません。また、寄付された物資が誤用されることもほとんどありません。しかし、災害時には、複数の組織が効果的に協力し合うことが課題となります。最初の48~72時間の間に、地元の自治体がある程度の情報を持っていても、それを公にすることはありません。これには正当な理由があり、パニックを避けるためでもありますが、より協力的なアプローチを取ることで、情報の一部をNGOに提供し、NGO側も情報を共有することで、より効果的な支援が可能になるかもしれません。
ジョエル:評価チームが現地に派遣される場合、交渉スキルはどの程度重要ですか?特に地元の役人との初対面で、拒絶されることなく情報を収集するためには、どのようなアプローチが必要でしょうか?
チャールズ:評価を行う担当者に求められるのは、基本的な礼儀や尊敬の気持ちを持ちながら関係を築こうとする姿勢です。政府とのやり取りにおいては、「情報を持っているか」「対応する余裕があるか」といった尺度を使って、コミュニケーションの状況を評価できます。各チームが異なる経験を持つことは良いことであり、それを統合することで、どの地域でどのような対応が可能かが見えてきます。
ジョエル:事前に特定の地域と協定を結んでおくことが重要だと感じますが、セカンドハーベストではいくつかの自治体と協定を結んでいると聞いています。大規模な災害が発生した場合、その協定がスムーズな支援につながると考えられますか?
チャールズ:必ずしもそうとは限りません。協定を結ぶことは重要ですが、最終的には現場の担当者との信頼関係が鍵になります。現場では、トップの人間が「寄付を受け入れる」と決めても、実際にそれを実行する人が「いや、やらない」と言えば、支援は動きません。そのため、協定はあくまで関係構築のスタート地点にすぎません。現場での信頼関係を築くことが最も重要です。
ジョエル:興味深いですね。交渉について、ハーバード・ケネディスクールでの学びを深めたと聞きましたが、日本に戻ってきてから、どのように活かされているのでしょうか?また、今後どのような場面で役立つと考えていますか?
危機管理ポッドキャスト「日本における人道支援のリスク」の他の記事
- 災害時の人道アクセスを考える
- 必要な資源を必要なタイミングで必要な人々に届ける
- 東日本大震災での支援におけるリスク
おすすめ記事





















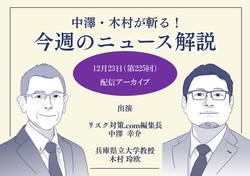

















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方