『熊本地震の経験を、日本全体の教訓に』(熊本県知事 蒲島郁夫氏)
危機管理のトップが学ぶべき点
リスク対策.com 編集長/
博士(環境人間学)
中澤 幸介
中澤 幸介
新建新聞社取締役専務、兵庫県立大学客員研究員。平成19年に危機管理とBCPの専門誌リスク対策.comを創刊。数多くのBCPの事例を取材。内閣府プロジェクト「平成25年度事業継続マネジメントを 通じた企業防災力の向上に関する調査・検討業務」アドバイザー、内閣府「平成26年度地区防災計画アドバイ ザリーボード」、内閣府「令和7年度多様な主体との連携による防災教育実践活動支援等業務」防災教育チャレンジプラン実行委員など。著書に「被災しても成長できる危機管理攻めの5アプローチ」、LIFE「命を守る教科書」等がある。
中澤 幸介 の記事をもっとみる >
X閉じる
この機能はリスク対策.PRO限定です。
- クリップ記事やフォロー連載は、マイページでチェック!
- あなただけのマイページが作れます。
災害時におけるトップの役割とは何か―。ひとたび大災害が発生すると、自治体の首長には一気に権限が集中します。災害対策本部の機能や業務内容は地域防災計画の中にも書かれていますが、災害対策本部長である首長がどのように状況を判断して決断・指示すればいいのか、いかなる責任を負うかについて具体的に明記されているものは見たことがありません。
熊本地震では、庁舎が使えなくなるなど、極めて困難な状況の中、各自治体は災害直後から情報の収集、避難者への対応などに奔走しました。その時、各自治体の首長は、何を考え、どう行動したのでしょうか? 最も困難な事態は何で、どうそれを乗り越えたのでしょうか――。
昨年末、熊本県から「熊本地震への対応に係る検証アドバイザー」に任命され、熊本県知事と県内8市町村長(震度6強以上の揺れを観測し、かつ、応急仮設住宅を建設した市町村)にインタビューを行い、これらの事実をオーラルヒストリーとしてまとさせていただきました。過去8回にわたり、各市町村長へのインタビュー内容を紹介してきましたが、最終回の今回は、熊本県知事の蒲島郁夫氏へのインタビューです。蒲島知事が手に持っているボードに書かれた言葉こそ、知事の災害後の意思決定の根拠となったもです。「ギャップ仮説」は、災害対応のリーダーに共通にあてはまるフレームワークとも言えます。
参照:熊本地震の発災4か月以降の復旧・復興の取組に関する検証報告書(http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_23049.html?type=top)
オーラルヒストリー№9 熊本県知事 蒲島郁夫氏
『熊本地震の経験を、日本全体の教訓に』
二度にわたって熊本を襲った震度7の揺れ。本震が発生した4月16日は、
熊本県知事蒲島郁夫氏の3期目の始まりの日であった。
地震直後の初動対応や、将来を見据えた復旧・復興の道筋、課題など、
蒲島知事のリーダーシップと熊本の経験を全国に発信し続ける思いを聞いた。
■基本情報
【職員】 4,151人 【面積】 7,409.32㎢
【人口】1,764,648人 【世帯数】713,776世帯
■被害の概要
【人的被害】
死者 252人、負傷者 2,720人
【住家被害】
全壊 8,665件、半壊 34,392件
一部損壊 153,941件
【庁舎等の被害】
県庁舎は、耐震化を実施済であり、壁や柱のひび割れ、仕上げ材(モルタルやタイル)の剥離、天井等の落下、空調設備の破損等の被害はあったが、建物の使用に関して問題はなかった。また、非常用発電用燃料タンクの増設により、庁舎の電源が落ちることなく、災害対応に支障が出なかった。
















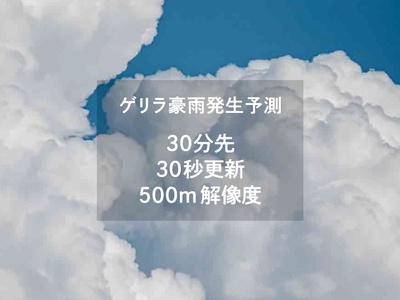











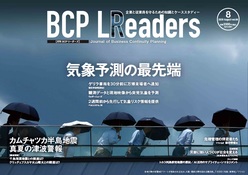



![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方