2018/04/10
熊本地震から2年、首長の苦悩と決断
現場の職員の声を信じる
過去に大雨や台風は経験したことがあるのですが、震度7の地震が2回も襲うということは経験がなく、とにかく大変でした。特に2回目の本震の時は、町長室で仕事をしていたのですが、命の危険を感じたことを今も覚えています。ただ、そうした状況の中で、町民の皆さんは役場に行けば何とかなるとの思いでやって来られます。
事実、前震の時は、役場の南側の駐車場に300人くらいの方が避難されました。まず、ありったけのブルーシートと毛布を職員に用意させました。マスコミ取材と思われるヘリコプターの音と、余震のたびに響き渡る避難者の悲鳴は、今でも私の耳に残っています。
指定避難所として1キロほど先に総合体育館があったのですが、余震も続いており、二次災害の恐れがあるため、総合体育館への移動は落ち着くまで待つという判断をしました。
避難者の方々には、夜明けを待ち自衛隊等の協力で総合体育館に移動してもらいました。しかし、総合体育館では、メインアリーナの安全が確認できず避難所として町民を受け入れることができない状況にありました。総合体育館では避難されている方が廊下に溢れている状況で、「なぜメインアリーナに入れないのか」との声もありましたが、現場の職員からの「メインアリーナの天井の一部が少し壊れている。」との報告や余震が続いている状況を踏まえ、メインアリーナには避難者を入れませんでした。
結果として16日の本震では、メインアリーナの1枚5.4キロある天井パネルや照明器具が全部落下しました。もし避難者をメインアリーナに入れていたら多くの死傷者が出ていたかもしれません。
様々な情報を正確に入れてくれたのは現場の職員です。やはり、現場の意見を信じて判断したことが良かったと思いますし、震災時の的確な判断の重要性を再認識しています。

災害時にトップがなすべきこと
震災当時は副町長も配置しておらず、意思決定者は自分しかいなかったため、当時の行動表を見返すと、5分刻みで次々と決断をしていく状況でした。
ちょうど大地震や大水害を経験した首長有志がまとめた小冊子「災害時にトップがなすべきこと」を机の中に入れていたので、前震後の15日にすぐに読み返して、がれき置き場の確保、ボランティアセンターの開設や罹災証明書の発行など、全体の流れを頭の中で描くことができました。これはとても役に立ち、15日には副知事に電話をして、県の13ヘクタールの土地を益城のために、がれき置き場として使わせてくださいと要請しました。
他にも、過去に震災などを経験した多くの自治体から災害の教訓をまとめた資料をいただき、とても役立ちました。今、益城町でも熊本地震に関する検証を行っていますが、地震前はまさか益城町でこのような大規模な地震が起こるとは思ってもいませんでした。
地震は、いつ何時どこで起きるかわかりません。全国の自治体トップの方には、ぜひ全国の災害を自分のことと捉えて、いろいろな災害の検証を見て、防災・減災に努めていただきたいと思っています。(益城町の震災検証結果につきましては、町ホームページに公表されています。)
初動における外部の支援
自衛隊、消防、警察の方々にはかなり早い段階から来ていただき、とても助かりました。最初に心配したのが火災だったのですが、発生は1件のみで、これは消防団がすぐ現場に駆け付けて消火してくれました。
また、15日と本震があった16日、17日の計3日間、すべての倒壊家屋について、下敷きになっている方がいないかローラー作戦で捜索をしてもらいました。早い時点での安否確認ができたことはとてもよかったと思っています。
一方、多くの職員が避難所運営に当たっていましたので、被害状況の確認や災害復旧などに、とにかく人手が足りない状況に陥りました。最初は職員がどこに誰が何人張りついているのか把握することができなかったのですが、2~3日した段階で確認ができ、それ以降は、毎晩、災害対策本部に課長全員に集まってもらって、20時から1時間ほど災害対策本部会議を行いました。会議では、町の被害状況、それぞれの現場や災害対策本部の対応状況などの情報共有や、喫緊の課題に向けた話し合いを行いました。
地域住民との顔の見える関係
町の職員も仕事や地域の活動で地域の方をよく知っており、避難所の運営でも顔見知りだと「これやってください」と言えます。しかし、日頃の関係がないと自分でせざるを得ず、抱え込んでいっぱいいっぱいになった面があり、地域の皆さんと顔見知りになることも非常に大事だったと感じています。
実は、地震前にあらかじめ部門横断的に地区ごとに担当職員を割り振る「地区担当制」を導入することを考えていたのですが、今後こういう取組が重要になってくると思います。
熊本地震から2年、首長の苦悩と決断の他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-










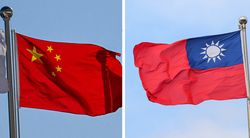















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方