新たな問題解決を導くAIと人間のハイブリッド
第44回:IT後進国から脱却できるのか(4)

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
2023/07/30
再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

Webなどで、過去のアクセス履歴やネットショッピングの実績から、お勧めの広告が表示されることは多くの方が実感されているだろう。これはお勧めするという意味で名付けられた「レコメンドシステム」によるものである。
実は、今回のコラムを書くにあたって、再度現状のAIの立ち位置などを調査・確認していた際に驚いたのは、このレコメンドシステムがAIの実施事例としてあげられていたことだ。
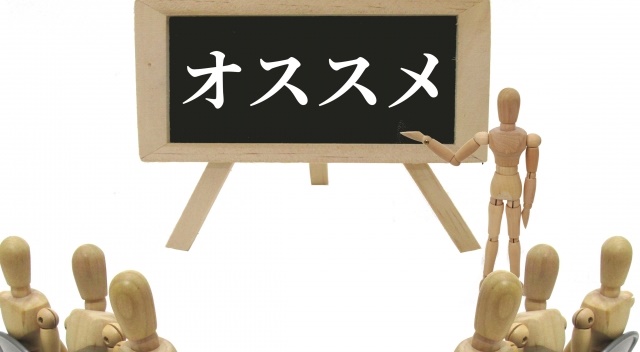
私自身、およそ20年ほど前であろうか、このレコメンドシステムの黎明期に、あるプロジェクトの責任者として、サービスにレコメンド機能を実装することになった。当時はAIなどという意識はまったくなく、事実、開発したサービスにAIは搭載していない。
そういう実績・経験もあって、いまのいままでレコメンドシステムとAIを結び付ける思考回路はまったくなかった。しかし、あらためていわれてみると、確かにと納得させられる一面もあるのだ。
まずは、レコメンドシステムについて説明していく。
黎明期のレコメンドシステムにおいて、大きく2とおりのエンジン、お勧めする機能のタイプが存在した。一つはルールベースエンジンであり、もう一つは協調フィルタリング方式のエンジンである。
前者のルールベースとは、その名のとおり、あらかじめ定められたルールに従って、お勧めを出力するエンジンである。この場合のルールとは、例えばAという商品を購入した人にはBをお勧めするとか、AとBを同時に購入した人にはCをお勧めするなどである。

このルールを定めるのは、マーケッターと呼ばれる人間である。マーケッターは、マーケットの基本定石を理解し、経営側の戦略的意思を受け、実際の取引や閲覧データを分析し、どのような施策を打つべきか提案する。施策としてはチラシ広告を打つエリアや、マス広告への展開などがあり、その一つに特定ターゲットへの発信もある。それらの効果を分析し、施策の有効性や是正点なども提案する。
有名なのは、スーパーマーケットでのバスケット理論事例「おむつとビール」が同時に購入されるという事象の発見である。後付けで原因を想定すれば、サラリーマンが帰宅時に奥さんからおむつを買って帰ってほしいと頼まれ、同時にビールに手が伸びるということらしいが、データの分析なく事前に想定するのは困難だろう。
このような効果を生み出すため、ルールとして施策を打ち、その結果を検証しながら、新たなルールを設定する、という作業を継続的に行うのだ。
したがって、ルールベースのエンジンはマーケッターの要望する複雑なルール設定をどれだけ実現するかが肝であり、それ以上でも以下でもないことから、比較的安価なシステム構築が可能ではある。しかし、マーケッターの腕が効果を左右し、運用上の負荷もマーケッターには相当大きなものになるのは避けられなかった。
再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事
おすすめ記事
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方