2020/03/11
福祉と防災

Q.被災者支援事業の効果、ポイントは?
【高橋氏への聞き取り】
[鍵屋コメント]
大震災後の復旧・復興事業で膨大な業務量を抱える中、気仙沼市は先駆的メニューを実施して、孤立死を防いできた。「おせっかいな相談員」による熱心な訪問が重要なのだ。被災者支援は、数字に表れないこのような対人支援の能力が大切だと改めて感じる。
一方で、国のやるべきことは高齢者の社会参加を目的とした集いの場(お茶っこ会)ではなく、フレイル予防をするための科学的根拠を明確にすること、それにより自治体が効果的な施策を進めやすくすることではないかと鋭く問いかけている。
Q.より効果的にするにはどうすればよいか?
【高橋氏への聞き取り】
[鍵屋コメント]
先進的に取り組んできた被災自治体の取り組みをパッケージ化、標準化して、次の災害ですぐに被災者支援に取り掛かることが重要だ。これは国の重要な責務ではないだろうか。
Q.課題は何か?
【高橋氏への聞き取り】
[鍵屋コメント]
気仙沼市でも、社会福祉協議会はボランティアセンターの運営だけで手一杯であり、他の日常業務が滞っている。そこに、地域支えあいセンターの運営まで任されると、間違いなく業務過多となる。連載第8回でも述べたが、ボランティアセンター運営業務の多くは、ボランティア団体に任せて、社会福祉協議会は地域福祉に注力するのが望ましい。
また災害後、要介護者が避難所や避難生活になると、ディサービスやコミュニティで活動する機会が少なくなり、介護度が高くなりがちである。直感的には、しっかりした被災者支援事業が、介護の重度化を予防し、介護保険給付増加の歯止めになると思われるが、自治体予算を使う以上、科学的根拠が欲しいところだ。
資料:「支え手になったあの日から‐地域を見守る支援員の語り 東北学院大学社会学研究室生活支援員聞き書きプロジェクト」2018年、発行者 宮城県サポートセンター支援事務所(宮城県社会福祉士会)
福祉と防災の他の記事
おすすめ記事
















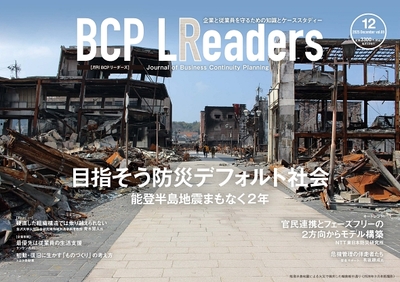



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方