2020/03/04
中小企業の防災 これだけはやっておこう
2. 火災発生時に求められる初動対応
火災発生時の初動対応には「通報」「初期消火」、そして「避難」という流れがありますが、出火の状況によってその優先順位は変わります。冷静な判断をして、逃げ遅れないようにします。
(1)通報
火災を発見した場合は「火事だ!」と大きな声で2回以上叫び、周囲の従業員に知らせ、その後の対応を大勢で進めることが重要です。また、声が出ないときは、物を叩くなどして知らせましょう。
さらに、落ち着いて119番通報することが求められています。小さな火災でも通報することが重要です。
(2)初期消火
必ず複数の従業員で消火活動に当たることが大切です。消火器から薬剤が出る時間は想像しているより短いため、火元付近にある消火器、そして別の階にある消火器を出火場所に集め、一気に初期消火を進めます。また、屋内消火栓も忘れず活用しましょう。
消火活動中に少しでも危ないと感じたとき、また炎が天井に達した場合などは、無理をせず避難します。逃げるに当たっては、逃げ遅れる従業員がいないことを確認するとともに、防火戸を閉鎖します。
地震発生時に起こる火災の場合は、大きな揺れでケガをしている従業員がいる可能性がありますので、自力避難できない人を避難場所まで搬送します。
(3)避難
避難に当たっては、火災現場である部屋の窓やドアを閉めて空気を遮断します。煙を吸い込まないように、姿勢をできるだけ低く保ちつつ、ためらわず、一気に走り抜けます。また、一度避難し終えたら、二度と建物内には戻りません。
避難終了後は、点呼などにより全員の避難が完了したかどうか確認し、逃げ遅れた従業員がいると分かった場合は、すぐ消防隊に報告します。
避難では、次の点にも注意が必要です。
①避難経路の選択
避難の際は、もちろん出火場所を避け、煙の被害を受けない経路を選択することが大切です。さらに、出火場所付近の階段は使えない可能性が高くなりますので、平常時から2つ以上の避難経路を考えておきましょう。エレベーターは、火災による停電で避難途中に停止することが考えられるため、使用不可です。
②誘導方法
大きな声で、どこから、どこに避難するかを、ハンドマイクなどを使い指示します。誘導に携われる人数が少なく、一度に多くの人数を誘導できない場合は、一時的に屋外階段の踊り場など安全な場所に避難してもらい、その後、地上に誘導することも考えましょう。
3. 消防訓練
火災による被害を最小限にするためには、消防隊が火災現場に到着するまでの間に、自社の従業員が初期消火をどれくらい的確に実践できるかどうかにかかっています。「ぶっつけ本番」で消火活動に当たっても、うまくいくものではありませんので、事前に行う消防訓練が重要となります。
また、防火管理者を選任している防火対象物については、消防計画に基づいて、通報、消火、避難の訓練を実施しなければなりません。特に不特定多数の人が出入りする防火対象物の場合は、消火・避難訓練を年2回以上実施することが求められています。
あわせて、訓練をする場合は、あらかじめ管轄の消防署または出張所に連絡することも必要です。
【ここがポイント】
火災は、まず、さまざまな防火対策でその発生頻度を下げることが重要です。その上で、的確な初動対応を実践することで被害を最小限にとどめます。
1. 平常時からの火災リスクを下げる取り組みが重要
2. 初動対応は「通報」「初期消火」、そして「避難」が基本
3. 消防訓練で防災力を高める
中小企業の防災 これだけはやっておこうの他の記事
おすすめ記事
-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/09
-

-

-

-
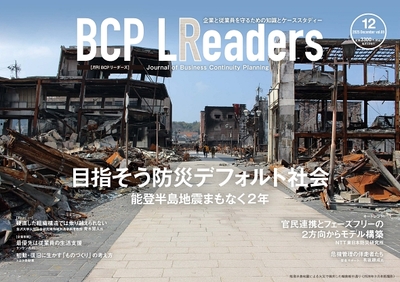
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/12/05
-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる
予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。
2025/12/04
-

























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方