2020/02/10
リスクは連鎖する!
3. 投資協定における仲裁判断とその執行
投資先国が投資協定上の約束を反故にした場合、投資家は仲裁を提起できることは先にも述べた通りだが、このことを規定しているのがISDS(Investor-State Dispute Settlement)条項といわれるものである。投資家は、ICSID条約、ICSID追加的利用手続き、UNICITRAL(United Nations Commission on International Trade Law)など、当該ISDS条項規則に従って仲裁手続きを進行することになる。「ISDS条項批判の検討-ISDS条項はTPP交渉参加を拒否する根拠となるか-」(*1) によると、仲裁の一般的な流れとしては、まず、仲裁人が選任される。通常は、投資家と被申立国が一人ずつ選出し、3人目の仲裁人は両者の合意で決定される。次に3人の仲裁人の多数決により、仲裁地が選定される。
仲裁廷が設置されると、仲裁廷はまず、付託された投資紛争について、仲裁廷が管轄権を有するか否かを判断する。管轄権が肯定されれば、受入国による義務違反の有無と、さらに義務違反が認定された場合には損害額の算定が行われる。
判断が確定し相手国がその判断に従わないと、執行が行われることになる。ICISD仲裁の場合はICSD条約の53条から55条に執行についての規定があり、それ以外の仲裁については、ニューヨーク条約(仲裁判断の承認及び執行に関する条約)(*2) 3条に基づき執行を行うことになる。
ここで問題となるのが果たして本当に執行が実行されることにより、投資家の損害額が回収できるのかということである。まず、ICSID条約では54条で以下のように定め、ICSID仲裁判断を執行する義務を締約国に課している(*3)。
一方、同55条では以下のように、執行を免除するような条項が入っている(*4)。
つまり、ICSID条約では、執行を義務づける規則(54条)と執行を妨げる執行免除の規則(55条)が並存していることになる(*5)。その結果、ICSID仲裁において執行が問題になった案件が、いくつか出現してきている(Liberian Eastern Timber Corporation事件とAIG Capital Partners事件については、以下に参考文献として挙げた独立行政法人経済産業研究所 RIETIディスカッション・ペーパー名古屋大学 水島朋則「投資仲裁判断の執行に関する問題」に記載の内容より、筆者がまとめた)。
たとえば、Liberian Eastern Timber Corporation (LETCO)事件では、リベリアでの森林管理に関するコンセッション契約の終了をめぐる投資紛争に関して、リベリアに対して補償を求めたものである。1986 年にICSID がLETCOに有利な仲裁判断を行ったが、リベリアが履行しないため、アメリカにあるリベリアの財産に対する執行を求めた事例である(*6)。ところが、この執行につき、アメリカの連邦裁判所ニューヨーク南部支部は、リベリア側からの反論により、アメリカの連邦外国主権免責法に基づき、当該リベリアの財産が主権的財産であるため、執行はできないと判断してしまった。LETCOはこの決定を受け、駐米リベリア大使館の銀行口座に対する強制執行の令状も獲得したが、この令状も連邦地方裁判所コロンビア特別区支部に、主権免責により、無効とされてしまった(*7)。
また、AIG Capital Partners (AIGCP) 事件は、カザフスタンにおけるジョイント・ベンチャーの財産の収用をめ ぐる投資紛争が、アメリカ=カザフスタン投資協定に基づいてICSID 仲裁に付託され、2003 年に出された仲裁判断をカザフスタンが履行しないため、執行を求めた事例である(*8)。AIGCPは、イギリスにおいて、ABN AMRO Mellon Global Securities Servicesが管理しているカザフスタン中央銀行の現金・有価証券に対して執行を求めたが、カザフスタン中央銀行は、この現金・有価証券はあくまで中央銀行の財産であり、商業目的で使用されているのものではないので、イギリスの国家免除法において執行からは免除されている財産だと主張した。イギリスの裁判所は、カザフスタン側の主張を取り入れ、この財産に対する執行はできないとした。
一方、ICSID仲裁以外の仲裁は、前述の通りニューヨーク条約に基づき執行することになるが、このニューヨーク条約に基づき執行を行っても、上記ICSID条約で起こったような執行拒否は起こり得る。要は、主権的財産に対して執行できないという国際法の解釈があり、何が主権的財産であるかは各国の裁判所に任されているが故である。なお、主権的財産の詳細については割愛するが、簡単に説明すると、国の財産(大使館や銀行預金などの外交使節団等の任務の遂行に使用される財産)、軍事的な任務の遂行に当たって使用される財産、当該国の中央銀行その他金融当局の財産、文化遺産、科学的、文化的、歴史的意義のあるものが含まれる財産等)は執行から免除されるが、「政府の非商業的目的以外により特定的に使用され」る財産(業務的管理的財産という)の場合は、執行措置を取ることができる(*9)。
リスクは連鎖する!の他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-











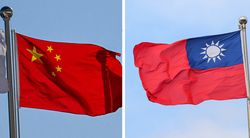














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方