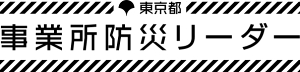2025/01/14
東京都事業所防災リーダー事務局

「東日本大震災が起きて多くの帰宅困難者が発生しました。当日は道路が渋滞し、家に帰ろうと歩く人が車道まで溢れ、大混乱に陥りました。それを契機に東京都が制定したのが帰宅困難者対策のための条例です。その大きな柱の一つは、首都直下地震のような大きな災害が起きた場合には、事業所は従業員を帰らせることなく、3日間程度は留まれるように準備をしておかなければならない、というものです」
これが『東京都帰宅困難者対策条例』 で、『自助』、『共助』、『公助』の考え方に基づき、帰宅困難者対策を総合的に推進するために平成24年3月に制定し、平成25年4月に施行された。その条例のポイントとなるのが帰宅困難者をむやみに移動させない「一斉帰宅抑制」だ。そのための事業所の備えについて、西平担当課長は次のように語る。
「具体的には、従業員1人あたり3日分の備蓄の用意。さらに3日間にわたり従業員が待機できるスペースを設けておくことを求めています。災害が起こった直後には、家族との安否確認が必要になるので、その方法を各自で取り決めてもらったうえで、事業所にいる人は基本的に3日間は自宅には帰らずに留まってもらう、それができる環境の整備をお願いしています」
家族と安否確認がとれたとしても、学校に通う子どもや施設に通う高齢者などの世話をするために帰宅したいと思う人は多いと思う。しかし東京都においては、条例で、学校などに対し児童生徒の施設内待機や安全のための必要な措置を講じるよう定めてあるので、皆が『家に帰らないこと』が、むしろ安全につながるのだという。しかし、条例が求めている企業などでの備蓄の確保等の一斉帰宅抑制の取り組みは道半ばだ。そこで東京都が特に力を入れているのが、零細企業や飲食店、美容院などの店舗も含めたあらゆる事業所での防災準備の推進だ。
「東日本大震災から時間が経過し、東京商工会議所での調査の結果、『東京都帰宅困難者対策条例』の認知度は低下傾向にあります。東京都でもガチャピンとムックのキャラクターを起用した広報動画などを作成し、『帰らない選択が、あなたを守る。』という啓蒙に努めてまいりましたが、さらに実効性の高い取り組みをするために『事業所防災リーダー』を設け、これを推進しています」
事業所内に備蓄をしたり、スペースを作ろうと思っても、誰かが率先して準備をしなければなかなか進まない。またいざ発災となるとさまざまな情報が飛び交い、どれが正しい情報なのかを素早く的確に判断することも難しくなる。そんなとき『事業所防災リーダー』がいれば、平時から的確な備蓄の知識やノウハウを知り、発災時には東京都が発信する災害情報を直接入手して、他の社員やスタッフに正しい指示を出すことができるというわけだ。西平担当課長はこう例える。
「『事業所内の防災対策を推進する旗振り役』が『事業所防災リーダー』です。防災リーダーとして対策を推進するためには、正しい情報を得ることが何より大切になります。その点、『事業所防災リーダー』になれば、発災時には東京都が発信する確かな情報がダイレクトに届き、また平時においては、防災のためのさまざまな知識が入手できるので、個人や事業所のための防災対策教育ツールとしても役立てることができます」
そしてこの『事業所防災リーダー』が、帰宅困難者対策に大いに有用だという。
「我々の被害想定では、首都直下地震の場合、約453万人が帰宅困難になるとされています。この帰宅困難者対策の1丁目1番地が、むやみに移動しないということ。熊本地震のときのように、大きな地震の直後にさらに大きな地震が発生することもありますし、火災や土砂崩れに巻き込まれたり、余震による落下物や瓦礫による怪我、帰ろうとする多くの人が集中して群集雪崩に遭う危険もあります。また発災後には、火災や倒壊した建物からの救出のために全国から警察、消防、自衛隊の応援部隊が駆けつけます。その道を大量の帰宅困難者が塞いでしまうことで、助けられる命が助けられなくなることもありえます。『むやみに帰らない』ということは、せっかく助かった自分の命をさらなる危険にさらさないためでもあり、さらに、他の人の命を救うために必要なことなのです。ですから、帰宅せずに事業所に安心して留まることができるように準備をすることが不可欠で、それを推進する役目を担うのが、『事業所防災リーダー』なのです」
事業所の防災力の底上げを図るためにも、そして、大災害から多くの人を救うことにもつながる『帰らない』という選択のために、より多くの事業所で『事業所防災リーダー』を育てることが求められている。
『事業所防災リーダー』になるのは難しくありません。
必要なのは簡単な登録だけ。
事業所内で何人ものリーダーを登録することも可能です。