災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~
【第2章】 「災害心理学」について
勇気の心と寄り添う心
株式会社日本防災デザイン /
CTO、元在日米陸軍消防本部統合消防次長
熊丸 由布治
熊丸 由布治
1980年在日米陸軍消防署に入隊、2006年日本人初の在日米陸軍消防本部統合消防次長に就任する。3・11では米軍が展開した「トモダチ作戦」で後方支援業務を担当。現在は、日本防災デザインCTOとして、企業の危機管理コンサルや、新しい形の研修訓練の企画・実施を行う一方、「消防団の教育訓練等に関する検討会」委員、原子力賠償支援機構復興分科会専門委員、「大規模イベント開催時の危機管理等における消防機関のあり方に関する研究会」検討会委員、福島県救急・災害対応医療機器ビジネスモデル検討会委員、原子力総合防災訓練外部評価員、国際医療福祉大学大学院非常勤講師、(一社)ふくしま総合災害対応訓練機構プログラム運営開発委員長等の役職を歴任。著作:「311以後の日本の危機管理を問う」、オクラホマ州立大学国際消防訓練協会出版部発行「消防業務エッセンシャルズ第6改訂版」監訳、「危険物・テロ災害初動対応ガイドブック」等。
熊丸 由布治 の記事をもっとみる >
X閉じる
この機能はリスク対策.PRO限定です。
- クリップ記事やフォロー連載は、マイページでチェック!
- あなただけのマイページが作れます。
一昨日は、あの忌まわしい東日本大震災から6年の歳月を迎えた日だった。この場をお借りして最愛のご家族やご友人を亡くされた方々に心より哀悼の意を捧げます。 筆者が長年任務に就いていた米軍を辞めるきっかけとなったのが、この大震災であると言っても決して過言ではない。ふと、30数年に渡り米軍で受けてきた教育や訓練を、一人の日本人として日本へフィードバックすることによって何か貢献出来ることがあるのではないかという思いが芽生えた日でもあった。あの時に思った感覚は今でも鮮明に思い出すことが出来る。
『備えていたことしか、役には立たなかった。備えていただけでは、十分ではなかった。備え、しかる後にこれを超越せよ。整備局の熟練した職員こそ、究極の「備え」である!』
これは、某省庁の方が、3.11の教訓として残した名言である。 筆者はこの言葉の究極の意味するところは、「災害時に戦える“人材育成”」であると断言する。つまり、それはこのシリーズでも繰り返し強調しているように、災害時に対応するのは一人ひとりの人間がチームとして機動力を発揮できるかという事だ。対応力を高めるためにはどうすれば良いのか!?
それは、正しい知識と技術をチームで実践するための体系的な仕組みを整備し、教育と訓練を繰り返し行うことでしか解決できないと思っている。内閣府のデータでも、津波被害においては、訓練をするかしないかで13%の被害者が減少するとされ、例えば、南海トラフ地震では、津波想定被害が23万人生じるとされている。
ならば、教育訓練を徹底すれば、「23万人×13% = 2.76万人」のかけがえのない命が救えるといえる。 このデータが示すように少しでも多くの人命を守るためには、微力ではあるが、「教育訓練」の仕組みが整備できるよう、今自分が出来ることを精一杯貫こうと決心した日だった。
そんな中、今回の第2章「災害心理学」の内容は、全シリーズの中でも、より多くの読者の方に読んで頂きたいと思っている。
■災害心理学
日本は戦前戦後を含め、過去にありとあらゆる種類の災害を経験してきた。ある意味、ここまでの経験をした国は希少かもしれない。読者の中にも過去に大きな災害に遭遇した方はいると思う。しかし、大多数の人が大規模災害の未経験者ではないだろうか?
今回の連載では、災害の体験者は過去の記憶と照らし合わせて被災者または救助者としての感情の変化を整理し、体験者でない方は擬似被災者として災害時に及ぼす心理的影響を予習していただきたい。また災害対応にあたる自主防災組織、自衛消防組織やボランティアの方々のためにも、事前に救助者としての心理的影響を予習していただきたい。
助ける側、助けられる側、双方に及ぼす精神的、身体的影響を解析することにより、事前知識として対応策を知っていれば特殊な状況下の現場においても、個人として、またチームとして、どのように対処すればよいかの助けになるだろう。災害対応を的確に実践するにはチームプレーが求められるが、特に混乱する災害現場において、人間の心理は“人との関わり”が大きなキーワードとなってくることを忘れないでいただきたい。
それでは災害時の精神的トラウマ、チームとしての安定、被災者と向き合う姿勢をひもといていこう。
【発災直後の心理的影響】
過去に発生した様々な大災害を被災者の観点から見ていくと様々な発見がある。まず、過去の災害の生存者からの様々な証言と犠牲者に見られる共通しているパターンをいくつか例として紹介していこう。
2001年9月11日午前8時46分、飛行中にハイジャックされたアメリカン航空ボーイング767が世界貿易センターのノースタワーに衝突した。9・11全米同時多発テロ事件の序章である。そのときタワー内にいた生存者の心理状態はどうだったのであろうか。
飛行機が時速784kmでビルに衝突し4つのフロアーが一瞬で消えたのだから、当然その衝撃は小さなものではなかったはずだ。しかし後に生存者を調査して分かったことは、階下への避難行動を取るまでに平均6分かかり、40%が脱出する前に私物をまとめたり電話をしたりコンピューター作業をしていたということだ(犠牲になられた方の数を加えるともっとこのパーセンテージは増えるはずだ)。
なぜ人は命の危険が目前に迫っているときにこのような行動を取るのだろうか?雑誌「火災予防工学」に掲載された論文には次のように書かれている。「人は火災の時、よく無関心な態度を取り、知らないふりをしたり、なかなか反応しなかったりした」。1980年11月に発生した栃木県の川治プリンスホテル火災、2003年に韓国で起こった地下鉄火災や2012年5月に発生した広島県の福山ホテル火災がそれを如実に物語っている。
川治プリンスホテル火災は、大浴場と女子浴場の間にあった露天風呂の解体工事の際、作業に使っていたガスバーナーの火花が浴場棟に燃え移った。火災報知器のベルが鳴ったが、従業員は確認もせず、「これはテストですから御安心下さい」という館内放送を流し、結果、宿泊客や従業員ら合計45名の死者を出した。
韓国地下鉄火災は、自殺願望の男が飲料用ペットボトルからガソリンを振り撒いて放火し火災となった事件だ。火災発生時、地下鉄の指令センターは状況を正しく把握しておらず、火災報知機が誤作動したと思い込み運転中止措置を取らなかったことが被害を大きくし、192人の死者が出た。
記憶に新しい広島県の福山ホテル火災は、7人が死亡した。建築基準法および消防法に違反した建築物を使用し長年営業していた上、行政側も見過ごしていたことが被害拡大を招いたとされていたが、2013年5月に総務省が発表した火災原因調査結果によると、消火器および屋内消火栓設備を用いた消火活動が行われていないこと、第一発見者による通報および有効な避難誘導が行われていないことが明らかになっている。
これらの火災は事業者側による責任も重大だが、生存者と犠牲者の命運を分けた違いは何だったのだろうか?
私達人間は、異常な事態が発生した時に無意識のうちにいくつかの「心のメカニズム」が働くことが明らかになってきている。心理学者はそれを“正常性バイアス”“集団同調性バイアス”“エキスパートエラー”などと呼んでいる。
それぞれの詳しい解説は専門書に任せるとして、このような心理的働きにより現実を否認したり、「みんなでいれば怖くない」的な根拠の無い感覚に陥り、避難を先延ばしにしたり、誰かの言葉を鵜呑みにして犠牲になるパターンがとても多い。犠牲者のすべてがこうした心理に陥っていたと言う気は毛頭ない。最初から適切な避難行動をとりながらも逃げ切れなかった方もおられるだろう。
しかし、大切なことは、災害時において起こりうる様々なバイアスを個人個人が理解することにより、瞬間的に自分自身の頭のスイッチを災害モードに切り替え生存するためのアクションにつなげなければならないということだ。















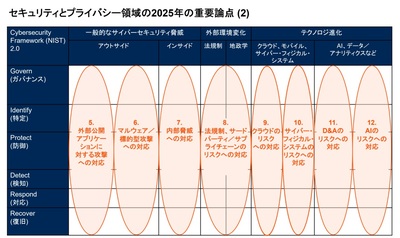



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方