2014/05/13
防災・危機管理ニュース
慶應義塾大学環境情報学部長の村井純教授が代表を務める「第1回防災情報社会デザインコンソーシアム」が5月12日、慶應義塾大学三田キャンパスで開催された。
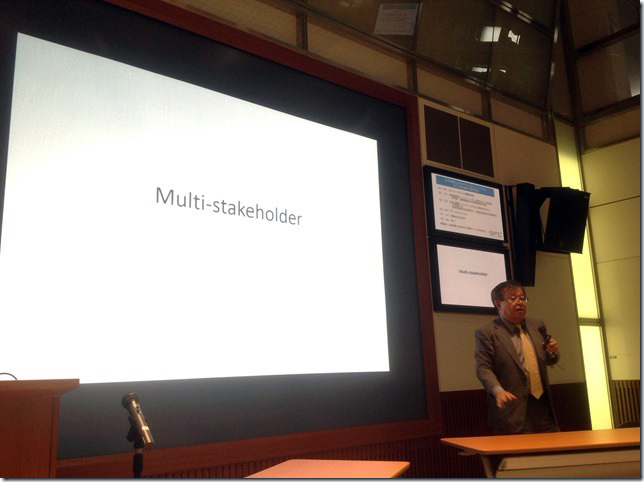
同コンソーシアムは東日本大震災の経験を踏まえ、防災や復旧・復興活動における情報通信技術やデザインの活用に関する知見を集約し、新しい防災の取り組みを実現することを目的として2013年1月から活動を開始した。村井教授は「コンソーシアムが果たすべき役割」と題して基調講演を行い、マルチステークホルダーによる防災・減災情報の連携の必要性を訴えるとともに、「災害に対するいろいろな思いがそれぞれにあると思う。それを話し合う場を作り、皆で議論を深めていきたい」と話した。
そのほか、これまで活動してきたプロジェクトの結果発表が行われ、「生き残るための新しい防災教育」の報告では慶應義塾大学環境情報学部の大木聖子准教授は小学校から大学までの新しい防災教育の取り組みについて、同大学法科大学院非常勤講師で弁護士の岡本正氏からは「巨大災害を生き抜く防災リテラシー」について、それぞれプレゼンがあった。岡本氏は「防災情報というとICT技術がクローズアップされがちだが、情報を活用し、災害に強い社会を作ることがコンソーシアムの目的。(プロジェクトでは)災害後に企業や個人が再興するための防災リテラシー研修のパッケージ化も考えていきたい」と話す。
<当日のプログラム>
基調講演「コンソーシアムが果たすべき役割」村井純氏(慶應義塾大学環境情報学部長)/特別講演「コンソーシアムに期待すること」/平本健二氏(経済産業省CIO補佐官/内閣官房政府CIO補佐官)/「防災情報データの標準化」武田圭史氏(慶應義塾大学環境情報学部教授)/「ITを活用した災害時の意思決定支援」宮川祥子氏(慶應義塾大学看護医療学部准教授)/「IT防災インデックス(指標)の確立」武田圭史氏(慶應義塾大学環境情報学部教授)/「生き残るための新しい防災教育」大木聖子氏(慶應義塾大学環境情報学部准教授)/「巨大災害を生き抜く防災リテラシー」岡本正氏(弁護士、岡本正総合法律事務所)/「防災とデジタル市民社会」斉藤賢爾氏(慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員(訪問) )
【防災情報社会デザインコンソーシアム問合せ先】
慶應義塾大学SFC研究所
防災情報デザインコンソーシアム事務局
disain-admin@sfc.wide.ad.jp
Tel. 0466-49-3529 (慶応大学 村井研究室)
防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事




































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方